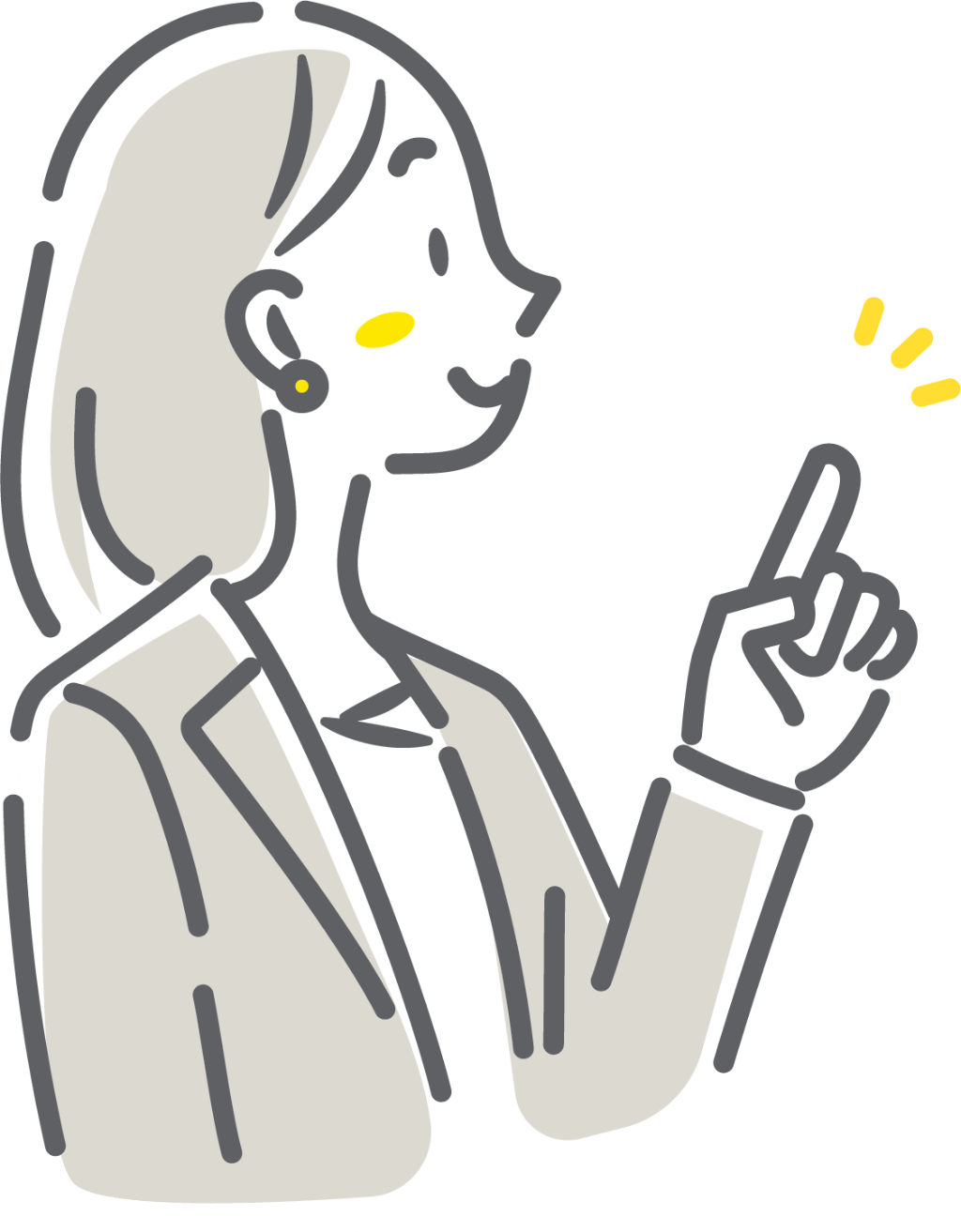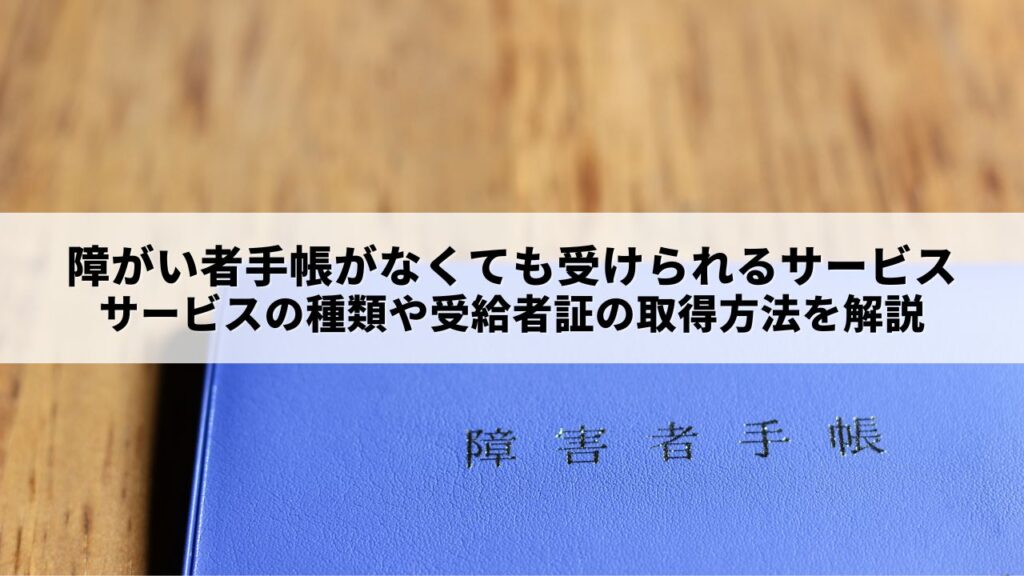
障がい者手帳とは、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
しかし、障がいがありながらも障がい者手帳の交付申請をしていない方や、申請するべきかどうか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
この記事では、障がい者手帳を保有していなくても利用できるサービスの種類や、受給者証の取得方法を解説します。
この記事を読むことで、障がいの程度や悩みに応じた適切なサービスが受けられるでしょう。
「運営のお悩み」9棟運営の経営者に相談できます
人材が定着しない。収益が伸びない。実地指導が不安。
月額3万円・初期費用0円で、現場を知る経営者が伴走します。
障がい者手帳がなくても受けられるサービス
障がいのある方が受けられるサービスの中には、障がい者手帳がなくても利用可能なサービスがあります。
ここでは、障がい者手帳の有無に関わらず利用できるサービスを解説します。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療は、精神疾患の治療を目的とした通院医療に対する支援です。
この制度は、自立支援医療(精神通院)支給認定申請をする必要があり、障がい者手帳を持っていなくても医師の診断書があれば申請可能です。
医療費の自己負担は基本的に1割ですが、所得の低い方や重度の障がいがある方には、月あたりの負担額に上限が設けられています。
自立支援医療受給者証が届くまでの間は、医療機関での費用は実費となるため注意が必要です。
障がい児通所支援
障がい児通所支援は、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用して専門的な支援を受ける制度です。
主に未就学児や就学児を対象としており、日常生活の基本的なトレーニングや対人関係の構築など、社会に適応できるような支援を目的としています。
障がい者手帳がなくても、自治体の保健センターや医師から療育の必要性が認められれば利用が可能です。
障がい児入所支援
障がい児入所支援は、18歳未満の障がいのある児童を対象としており、家庭での養育が困難な場合などに利用されます。
入所施設の種類は、以下のとおりです。
- 福祉型障がい児入所施設:主に日常生活の支援をする施設
- 医療型障がい児入所施設:医療的なケアが必要な子どもを対象とし、リハビリテーションと日常生活の支援を組み合わせたサービスを提供する施設
入所支援の利用により自己負担が発生する場合がありますが、具体的な金額は市区町村によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
日中一時支援
日中一時支援は、障がい者や障がい児が日中安全に過ごせるように一時的な見守りを提供している制度です。
この制度は、2つの目的により利用可能です。
- タイムケア:家族の就労などの理由により介護ができない場合
- レスパイト:障がい者を日常的に介護している家族の方の休息を目的としている場合
障がい者手帳を持っていなくても、自治体がサービス提供の必要性を認めれば利用できる可能性があります。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、障がいや難病を抱える方に働く機会や社会活動の場を提供する障がい福祉サービスです。
一般企業での雇用が難しい方や、年齢や体力的な理由で長時間働くことが困難な方が利用できます。
雇用契約を結ばずに働けるため、体調や生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は、障がいのある子どもが保育所や学校などの集団生活に適応できるように支援する福祉サービスです。
支援内容は、直接支援と間接支援の2つに分けられます。
- 直接支援:支援員が子どもに直接働きかけ、集団生活における困難を解決するための手助けをする。
- 間接支援:支援員が訪問先の保育士や教育スタッフに対して、子どもへの接し方や支援方法のアドバイスをする。
通常、支援は2週間に1回程度行われますが、子どもの状況に応じて頻度が変わる場合があります。
就労移行支援
就労移行支援は、障がいのある方が一般企業での就労を目指すために必要な知識やスキルを習得できる福祉サービスです。
職業訓練や就職活動の支援・生活リズムの改善など、利用者が自立した生活を送るためのサポートが受けられます。
障がい者手帳を持っていない方や精神的な不調で休職中の方も、主治医の診断書や意見書があれば利用可能です。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担額を一定の上限まで抑えられる制度です。
この制度は、1カ月に医療機関や薬局で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。
長期入院や重度の病気の治療が必要な場合に、家計への影響を抑えてくれます。
障がい福祉サービスの種類と支援内容
障がい福祉サービスには、上記で解説した制度の他にも、さまざまな支援があります。
ここでは、障がい福祉サービスの種類とその支援内容を解説します。
参考:厚生労働省『障害福祉サービスについて』
介護給付
介護給付は、障がい者が自立した生活を送るために必要な支援を提供する制度です。
サービスの種類は、大きく3つに分けられます。
- 訪問系:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者包括支援
- 日中活動系:短期入所・療養介護・生活介護
- 施設系:施設入所支援
サービスを利用するには、障がい者区分認定を受ける必要があります。
区分認定を受けることで、経済的な負担を軽減しながら生活の質を向上できるでしょう。
訓練等給付
訓練等給付は、障がい者が日常生活や社会生活を営むために必要なスキルの習得を支援する制度です。
サービスの種類は、大きく2つに分けられます。
- 居住支援系:自立生活支援・共同生活支援
- 訓練系・就労系:自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援
これらの訓練により、生活の質の向上や地域社会への参加を促進し、自分らしい暮らしを実現できるでしょう。
障がい者手帳なしで障がい福祉サービスを利用するには
障がい者手帳を持っていなくても、決められた手続きをすれば上記のような障がい福祉サービスの利用が可能です。
ここでは、障がい者手帳を保有していない方が障がい福祉サービスを利用する方法を解説します。
障がい福祉サービス受給者証の交付を受ける
障がい者手帳を保有していない方が障がい福祉サービスを受けるには、障がい福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
この受給者証は、サービスを受ける際に必要な証明書です。
また、受給者証を取得すると、サービスの利用料の一部または全部が公費で負担されます。
障がい福祉サービス受給者証の申請方法
障がい福祉サービス受給者証を申請するには、まず自治体の障がい福祉課や相談支援事業所に相談し、必要な書類や手続き方法を確認します。
申請書類は自治体によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。
- 利用申請書
- 本人確認書類
- 医師の診断書
障がい児の場合、学校への在籍が確認できる書類の提出を求められることがあります。
また、受給者証は有効期限があるため、期限が切れる前に更新手続きを済ませましょう。
障がいのある方が相談できる窓口と支援機関
障がいのある方が社会生活をしていく中で、困りごとや問題が生じる場合もあるでしょう。
ここでは、障がいのある方が悩みを相談できる窓口や支援機関を紹介します。
市区町村の福祉課
市区町村の福祉課は、障がい福祉サービスを含むさまざまな福祉サービスの提供と支援を実施する窓口です。
障がい者やその家族からの相談に応じ、適切なサービスの紹介や情報を提供しています。
受給者証を取得した後も継続的に相談に応じてくれるため、安心してサービスを受けられるでしょう。
地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターは、障がいを持つ方が職場でスムーズに働けるように支援をする機関です。
この施設では、障がい者が就職や復職をするために必要な専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。
地域障がい者職業センターを利用するためには、専門のスタッフと面談が必要です。事前に相談予約をしましょう。
合意した支援内容に基づいて、職業リハビリテーションや就職支援が開始されます。
参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構『地域障害者職業センター』
障がい者就業・生活支援センター
障がい者就業・生活支援センターは、障がい者の雇用促進や生活の安定を目的としており、地域のハローワークや福祉機関と連携しながら支援を提供しています。
利用対象者は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がいのある方や難病の方などで、障がい者手帳がなくても医師の診断書があれば利用可能です。
センターによっては、来所相談だけでなく電話相談などを実施している場所があるため、詳しくはお近くの障がい者就業・生活支援センターへご確認ください。
参考:厚生労働省『令和6年度障害者就業・生活支援センター一覧』
よくある質問
障がい者手帳の有無に関わらず利用できるサービスを紹介してきましたが、他にもさまざまな疑問がある方もいるでしょう。
ここでは、障がい者手帳や障がい福祉サービスに関するよくある質問を解説します。
障がい者手帳の代わりになるものはありますか?
障がい者手帳の代わりになる証明書には、以下のような書類があります。
- 障がい福祉サービス受給者証
- 医師の意見書
- 自立支援医療受給者証
- 障がい年金証書
- 特別支援学級や特別支援学校の利用実績
これらの証明書を持っている場合、就労継続支援A型やB型・就労移行支援などの障がい福祉サービスを利用できます。
しかし、障がい者手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引などさまざまな支援を受けられるため、可能であれば手帳の申請を検討すると良いでしょう。
就労継続支援B型は障がい者手帳がなくても利用できますか?
上記で記載したように、就労継続支援B型は障がい者手帳がなくても利用可能です。
就労継続支援B型を利用するためには、まずはお住まいの市区町村の障がい福祉課に相談し、受給者証の申請をする必要があります。
障がい福祉サービス受給者証のメリットは何ですか?
障がい福祉サービス受給者証のメリットの一つは、経済的負担の軽減です。
受給者証を取得すると、障がい福祉サービスの利用料の一部または全額が公費で負担されます。
また、障がい福祉サービスを提供する事業所との契約がスムーズに進むため、必要な支援を迅速に受けられるメリットがあるでしょう。
【まとめ】障がい者手帳がなくても受けられるサービスはある
障がい者手帳を保有していない場合でも、障がい福祉サービス受給者証の取得により、さまざまなサービスの利用が可能です。
受給者証の申請には、申請書や医師の診断書が必要となるため、自治体の障がい福祉課に相談の上、手続きを進めてください。
また、障がい福祉サービスの他にも地域障がい者職業センターなど、行政には障がいのある方の相談窓口があります。
障がいがあっても自立した生活ができるように、利用できるサービスを把握しておきましょう。
「運営のお悩み」9棟運営の経営者に相談できます
人材が定着しない。収益が伸びない。実地指導が不安。
月額3万円・初期費用0円で、現場を知る経営者が伴走します。