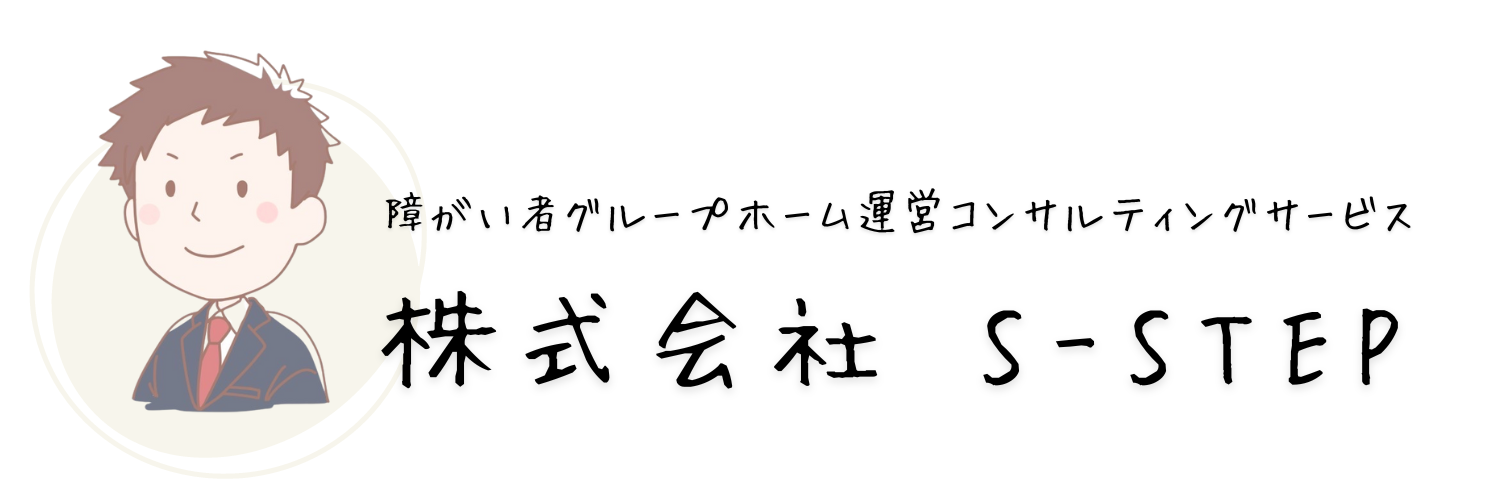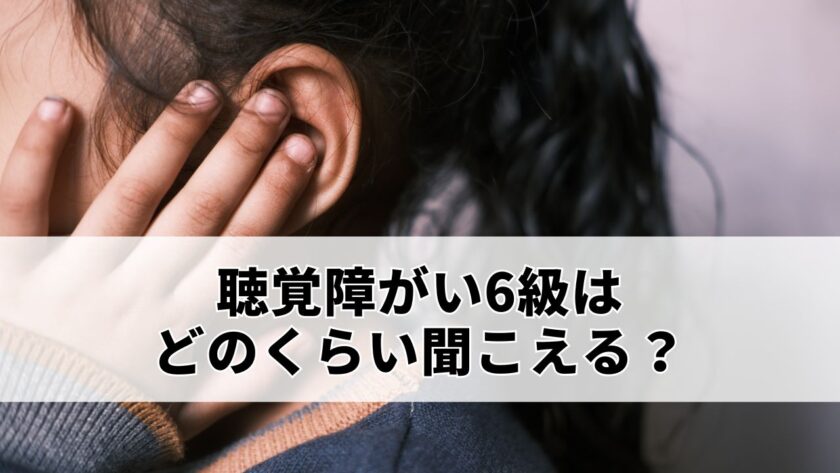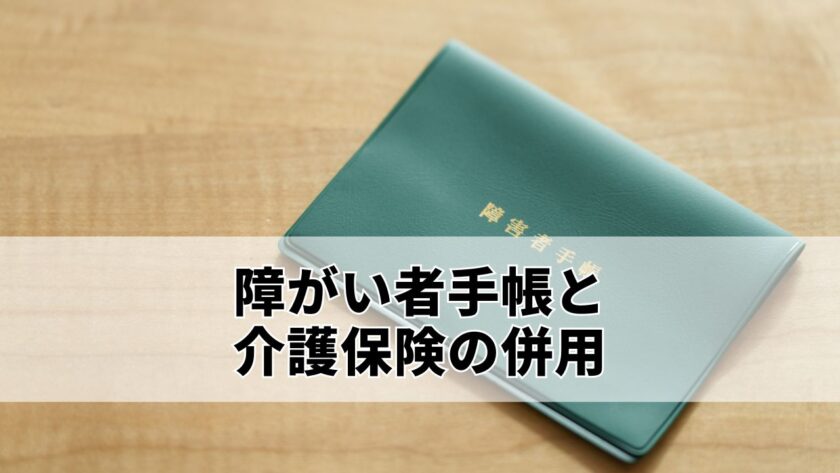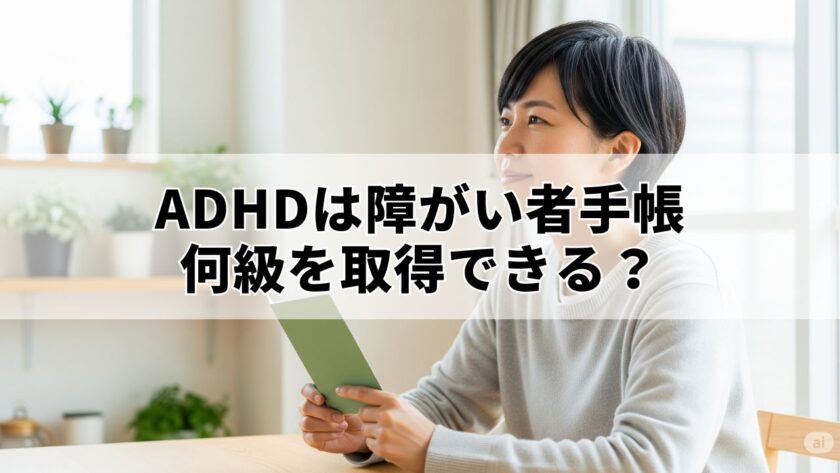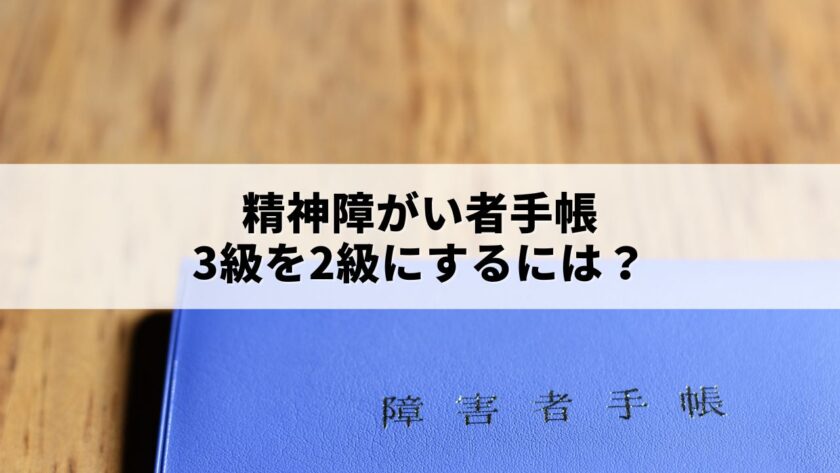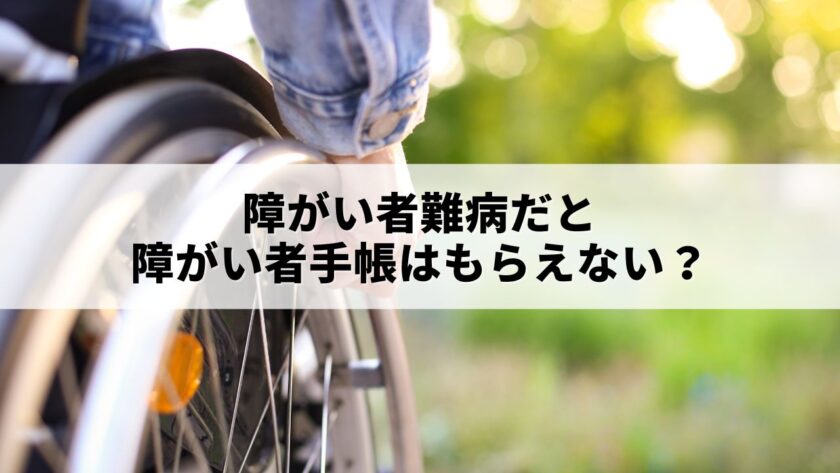精神障がい2級の障がいがある方の中には、運転免許の更新ができるかどうか不安に思っている方もいるでしょう。
病気の状態や薬の服用状況、これまでの症状などによって違いはありますが、安定した状態であれば通常の手続きでの更新が可能です。
この記事では、精神障がい2級でも運転免許を更新できる条件や更新手続きの方法を解説します。
この記事を読むことで、精神障がい2級の方が安全に運転免許を更新するための準備や手順を理解でき、手続きの不安を減らせるでしょう。
「新たな事業展開で収益を拡大したい」
株式会社S-STEPが、豊富な経験と独自のノウハウで、そんなあなたの思いを実現します!
✅ 開所準備から運営まで徹底サポート!
✅ 無駄なコストを削減し、スムーズな開所を実現!
✅ いつでも解約OK!安心のサポート体制!
放課後等デイサービスとの相乗効果で収益アップも可能。スタッフ採用、物件選定、煩雑な手続きなど、あらゆる課題を解決します!
精神障がい2級でも運転免許更新はできる
精神障がい2級と診断されていても、運転に支障がなければ更新手続きは可能です。
ここでは、精神障がい2級でも運転免許を更新できるケースを確認していきましょう。
一定の病気に該当しない場合
精神障がい2級であっても一定の病気にあてはまらない場合、運転免許を更新できる可能性があります。
運転免許の拒否や取り消しの対象となる病気は、以下のとおりです。
- 認知症
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- そううつ病・そう病・うつ病
- 無自覚性の低血糖症
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障がい
- アルコール依存症、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの中毒
- その他安全な運転に支障のある方
これらの病気に該当するものがなく、症状が安定していると判断された場合は、更新手続きができるでしょう。
参考:警視庁『運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について』
質問票に該当する項目がない場合
運転免許を更新するときには、健康状態についての質問票を提出します。
質問票には、以下のような質問が含まれます。
- 過去5年以内に意識を失ったことがあるか
- 身体の一部が一時的に動かせなくなったことがあるか
- 日中に活動中に眠り込んでしまったことが週3回以上あるか
- 医師から運転を控えるよう助言を受けたことがあるか
これらの項目にあてはまらなければ、追加の検査や診断書を提出しなくても、そのまま更新できることが多いです。
しかし、不安がある方は、更新日前に安全運転相談窓口で相談しておくと安心でしょう。
その際に、主治医に書いてもらった診断書や服薬状況・治療の経過がわかる資料があると、もしものときに役立ちます。
一定の病気に該当する場合の対応方法
運転免許の更新で一定の病気にあてはまると、更新手続きに特別な対応が必要になります。
ここでは、一定の病気に該当する場合の対応方法を解説します。
臨時適性検査を受ける
臨時適性検査とは、病気などが原因で安全な運転が難しいと思われる方に対し、公安委員会が指定した専門医が、運転能力の有無を判断するための検査です。
精神障がい2級の方でも、症状の程度により検査が必要になることがあります。
たとえば、統合失調症や重いうつ状態・てんかん発作の再発が懸念される場合など、運転に必要な認知や注意力に不安な要素がある方が対象です。
検査結果は、公安委員会が免許を更新するかどうかを決める材料になります。
医師が危険と判断した場合は、更新が保留または取り消しになることもあります。
まずは主治医に相談し、必要であれば運転免許試験場の安全運転相談室へ連絡して案内を受けましょう。
運転適性相談窓口を活用する
運転適性相談窓口は、病気や身体的な障がいで運転に不安のある方を対象とした相談機関です。
ここでは、運転に関する健康状態の確認や、医師の診断や検査が必要かどうかを相談できます。
具体的な窓口の連絡先や予約方法は、各都道府県の警察や運転免許センターの公式サイトで確認しましょう。
精神障がい2級の方の運転免許更新手続き方法
精神障がいがあっても、正しい手続きをすれば運転免許の更新ができます。
ここでは、運転免許更新時に提出する書類の内容と注意点、手続きの流れを解説します。
運転免許更新に必要な書類
免許更新をするすべての方に必要な書類は、以下のとおりです。
- 現在交付されている運転免許証
- 更新手数料
- 運転免許証更新連絡書(更新はがき)
一定の病気にあてはまる人や質問票で「はい」の項目がある人は、医師による診断書が必要になります。
診断書は、主治医と相談して正確に作成してもらうことが大切です。
診断書に間違いがあったり情報が足りなかったりすると、更新手続きが遅れたり追加提出を求められることがあります。
更新をスムーズに進めるために、事前に必要な書類を確認して、余裕をもって医師に診断書を依頼しましょう。
運転免許センターでの申告と手続きの流れ
運転免許センターでの手続きの流れは、以下のとおりです。
- 更新通知の受領
- 必要書類の準備
- 運転免許センターへの訪問
- 適性検査の実施
- 講習の受講
- 免許証の交付
医師から運転を控えるよう指示されている場合、その旨を手続きをするときに必ず伝える必要があります。
申告をしないと処分を受けることもあるため、正直に回答しましょう。
精神障がい2級の運転免許更新での注意点
精神障がい2級の方が運転免許を更新する場合、通常の手続きに加えて気をつけるべき点がいくつかあります。
ここでは、精神障がい2級の運転免許更新での注意点を解説します。
運転免許更新時は病状を正しく伝える
運転免許を更新するときは、過去の病気や症状に関しての質問票に回答する必要があります。
ここで虚偽の回答をすると、法律上の罰則が科せられる可能性があるため、正直に申告しましょう。
申告を正しく行わなかった場合、1カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
必要であれば、主治医に相談して診断書を用意しておくと安心です。
参考:神奈川県警察『運転免許の取得時や更新時の質問票提出について』
精神障がいによる事故は責任が問われる場合がある
病気のことを申告せずに車を運転して事故を起こすと、その責任がより厳しく問われることになります。
たとえば、薬の副作用で強い眠気が出る人がそれを隠して運転し事故を起こすと、自動車運転致死傷罪という罪にあたることがあります。
事故を防ぐためには、自身の症状をしっかりと理解し、更新時や日常生活で必要な安全対策をすることが大切です。
運転に不安がある場合は、安全運転相談窓口への相談や免許の自主返納を検討するなど、安全の確保を心がけましょう。
免許取り消し後は再取得が困難である
精神障がいが原因で免許が取り消された場合、すぐに免許を取り直すことはできません。
一定の期間様子を見たり医師に体の状態を確認してもらったりと、再取得までに時間がかかることがあります。
しかし、取り消しの原因となった病気や障がいが回復していることを医師の診断で確認できれば、再取得の申請が可能です。
また、取り消しから3年以内の再取得申請は、症状が安定していれば運転試験の一部が免除されることもあります。
再取得を考えている方は、医師による診断書や治療の記録を準備し、体の状態が落ち着いていることを証明できるようにしましょう。
よくある質問
運転免許の更新は、精神障がい2級を持つ方にとっても日常生活の自立に関わる大切な手続きです。
更新時には、病状や服薬の状況、運転に支障が出る可能性がある薬の使用など、確認されるポイントがあります。
ここでは、更新に関するよくある質問について解説します。
精神疾患で運転禁止の薬は?
精神疾患の治療に用いられる薬には、自動車の運転に影響を及ぼすものが多くあります。
特に、抗精神病薬や抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬・抗てんかん薬は、添付文書で運転に注意するよう明記されていることがほとんどです。
これらの薬は、人によっては副作用で眠くなったり注意力が下がったりすることがあります。
ただし、すべての服薬者に運転禁止が必要というわけではありません。
副作用の現れ方には個人差があるため、医師は薬の開始時や増量時に運転を控えて体調の様子を確認するよう指示することがあります。
その後も眠気やふらつきがないか確認し、安全を確認できれば運転を再開できます。
道路交通法でも、薬の影響で正常な運転ができない状態は違法とされているため、服薬中は体調の変化に注意して行動しましょう。
参考:公益社団法人日本精神神経学会『患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン』
病気療養中の免許更新はどうなる?
運転免許の更新期間中に病気で療養していた場合、更新手続きができなかった理由は「やむを得ない」として扱われます。
入院中や症状が重く通院が難しい場合も含まれ、精神障がいによる療養期間中も対象です。
失効から6カ月以内であれば、学科や技能試験は免除され、視力や聴力などの適性検査に合格すれば免許が交付されます。
失効から6カ月を超え3年以内では、やむを得ない事情が解消されてから1カ月以内に適性試験を受けることで更新できる場合があります。
【まとめ】精神障がい2級でも運転免許更新はできる
精神障がい2級であっても、運転に支障がなければ運転免許の更新は可能です。
病状が安定していて、運転に危険がないと判断されれば、通常の手続きや一部の適性検査で更新できます。
また、一定の病気や症状がある場合は、臨時適性検査や医師の診断書提出が必要です。
質問票に正しく記入し、症状や服薬状況を正直に伝えることで、手続きの遅れや不備を防げます。
運転免許を安全に更新するためには、事前に安全運転相談窓口や主治医に相談し、必要書類や手順を確認して手続きを進めましょう。
「新たな事業展開で収益を拡大したい」
株式会社S-STEPが、豊富な経験と独自のノウハウで、そんなあなたの思いを実現します!
✅ 開所準備から運営まで徹底サポート!
✅ 無駄なコストを削減し、スムーズな開所を実現!
✅ いつでも解約OK!安心のサポート体制!
放課後等デイサービスとの相乗効果で収益アップも可能。スタッフ採用、物件選定、煩雑な手続きなど、あらゆる課題を解決します!