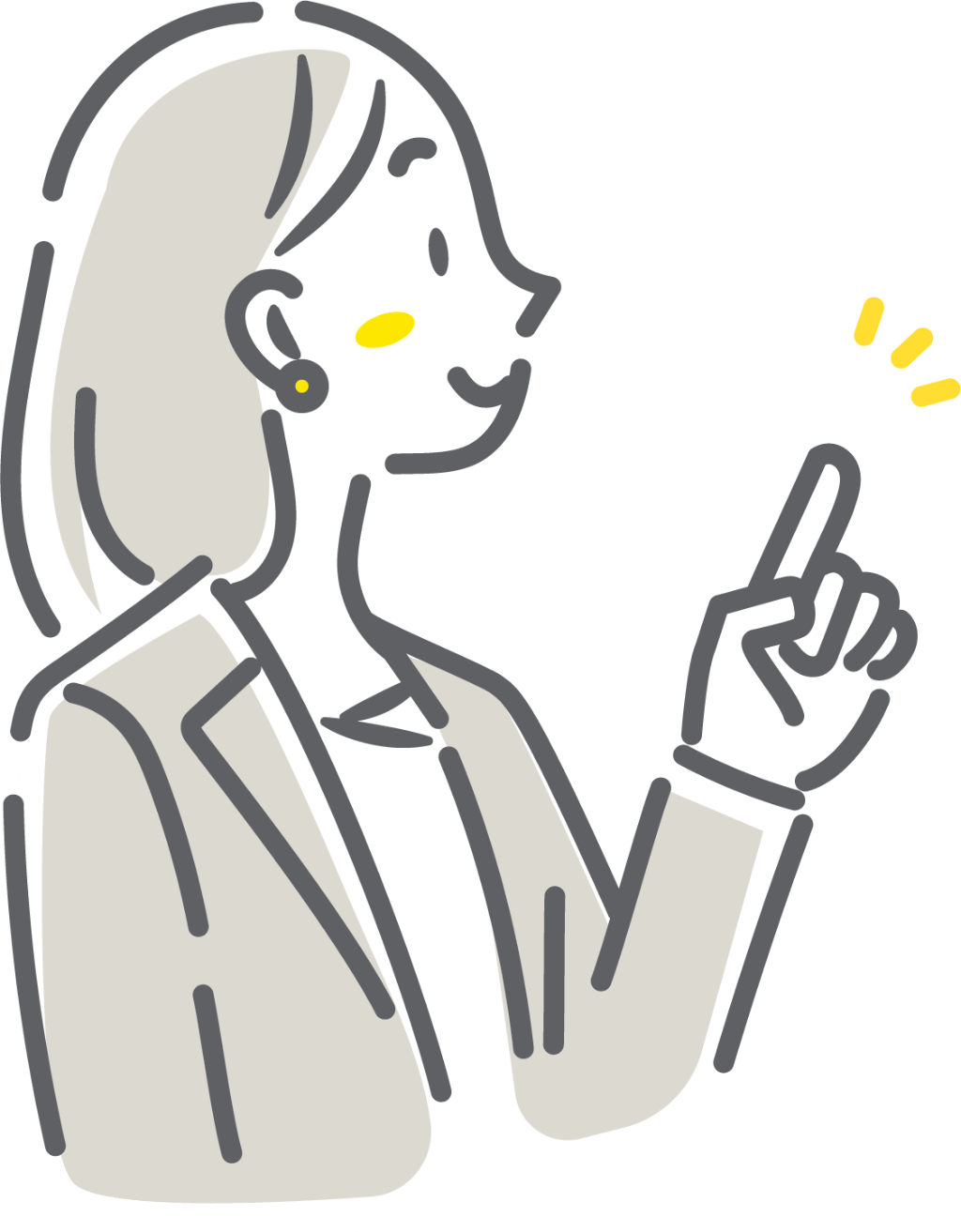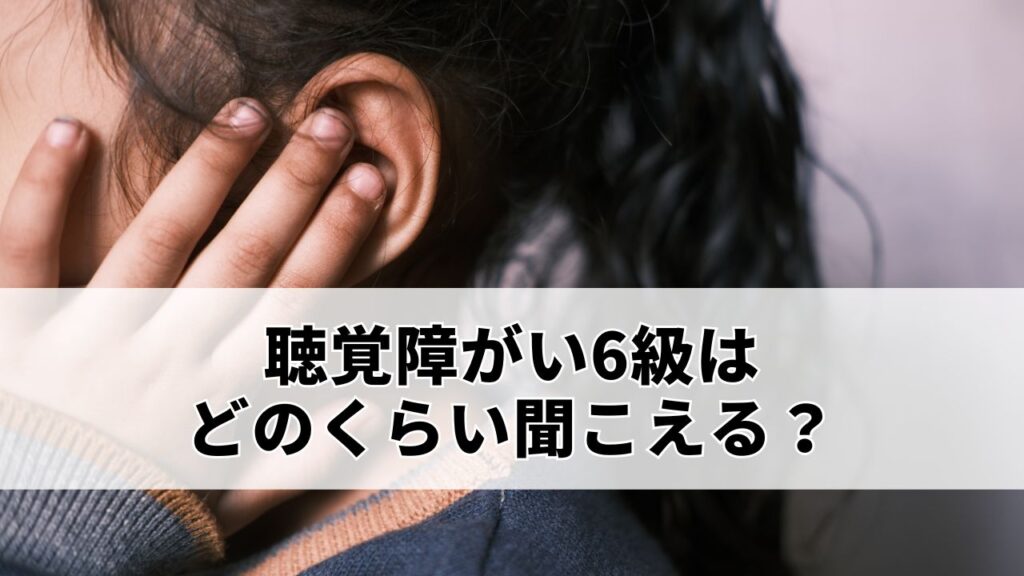
聞こえにくさを感じている方にとって、聴覚障がい6級がどのくらい聞こえるのか疑問に思っている方もいるでしょう。
聴覚障がいには等級があり、それぞれの等級ごとに基準が設けられています。
この記事では、聴覚障がい6級の認定基準や身体障がい者手帳の申請方法・支援制度について解説します。
記事を読むことで、聴覚障がい6級の具体的な聞こえ方が把握でき、制度を活用して日常生活をより快適に過ごせるでしょう。
「運営のお悩み」9棟運営の経営者に相談できます
人材が定着しない。収益が伸びない。実地指導が不安。
月額3万円・初期費用0円で、現場を知る経営者が伴走します。
聴覚障がい6級はどれくらい聞こえる?
聴覚障がいの等級は、日常生活にどの程度の支援が必要かを判断する基準となります。
ここでは、聴覚障がい6級の認定基準とほかの等級との違いを解説します。
聴覚障がい6級の認定基準
聴覚障がい6級は、聴覚障がいの中で最も軽度の等級に位置付けられています。
詳しい認定基準は、以下のとおりです。
- 両耳の聴力が70デシベル以上
- 片方の耳が90デシベル以上、もう片方の耳が50デシベル以上
70デシベルという音量は、騒がしいオフィス内の音量に相当します。
90デシベルはカラオケで歌っている室内程度、50デシベルは家庭用エアコンの室外機付近の音量が目安です。
通常の会話は約60デシベルの音量であるため、職場での会話や電話での会話も聞き取りが困難になるでしょう。
しかし、聴覚障がい6級は、補聴器を使用すればある程度の聞き取りが可能になる場合があります。
まずは専門医で聴力の状態を確認したうえで、適切な補聴器を選択しましょう。
参考:厚生労働省『身体障害者障害程度等級表』
ほかの等級との違い
聴覚障がいの等級は、5級を除く2級から6級まで設定されており、数字が小さいほど重度の障がいを表しています。
各等級の認定基準は、以下のとおりです。
- 2級(最重度):両耳の聴力レベルが100デシベル以上、両耳の聴力を完全に失った状態
- 3級(重度):両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 4級(中等度):両耳の聴力レベルが80デシベル以上、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
聴覚障がい2級は、日常会話はもちろん、耳元で話されても聞こえないため、手話や筆談が主なコミュニケーション手段となります。
3級は、耳元で話されても聞き取りが非常に困難で、補聴器を使用しても日常会話の理解は限定的になります。
4級は、大声で話されれば部分的に聞き取れる場合もありますが、通常の会話は困難を感じる状態です。
この認定基準を見てわかるように、6級とほかの等級は聞こえる音量の範囲に大きな違いがあります。
聴覚障がい6級で身体障がい者手帳を取得する方法
身体障がい者手帳は、聴覚障がいのある方がさまざまな支援や福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
ここでは、身体障がい者手帳の申請で準備すべき書類や流れ・注意点を解説します。
参考:千葉市『身体障害者手帳交付の方法・手順』
申請に必要な書類
身体障がい者手帳の申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
- 交付申請書
- 身体障がい者診断書・意見書
- 申請用の写真
交付申請書は、お住まいの市町村の窓口で入手できます。
診断書・意見書は、指定医師によって作成されたものが必要です。
自治体の窓口で診断書用紙を受け取る際に、指定の病院がどこなのかを確認しておきましょう。
申請の流れ
次に、身体障がい者手帳の申請の流れを確認していきましょう。
- 自治体の障がい福祉担当で申請書や診断書用紙を入手する
- 指定医師で純音聴力検査や語音明瞭度検査を受け、医師が診断書を作成する
- 作成した診断書と申請書・写真などを窓口へ提出する
- 審査終了後、障がい者手帳が交付される
申請から交付まで約1カ月から1カ月半程度かかる可能性があるため、余裕をもって申請手続きを開始しましょう。
申請時の注意点
診断書作成にかかる費用は、全額自己負担となります。
医療機関によって料金が異なるため、料金や支払方法は各医療機関で確認しましょう。
また、手続きの詳細や提出書類は、お住まいの市町村によって異なる場合があります。
インターネットで調べた情報だけに頼らず、必ずお住まいの障がい福祉担当課に直接問い合わせて、正確な情報を確認してください。
聴覚障がい6級で受けられる支援
身体障がい者手帳による制度を活用すると、日常生活における経済的負担を軽減し、より安心した暮らしを実現できます。
ここでは、聴覚障がい6級の方が受けられる支援について解説します。
税金の控除
障がい者手帳の保有により、所得税や住民税での障がい者控除や減免が受けられます。
所得税の障がい者控除は、年間27万円の所得控除が受けられ、特別障がい者や同居の有無で控除額が異なります。
所得控除や免税を受けるには、その控除等に該当することを申告しなければなりません。
給与所得のみの人は給与の支払者へ、そのほかの人は確定申告の際に税務署へ申告しましょう。
参考:国税庁『障害者控除』
各種交通機関などの運賃割引
身体障がい者手帳を提示すると、鉄道やバスなどで運賃の割引や優遇が受けられる場合があります。
鉄道会社では普通乗車券が半額になるケースが多く、長距離移動での経済的メリットが大きくなります。
利用したい交通機関や事業者に直接問い合わせて、具体的な割引内容や申請方法を確認しましょう。
日常生活の支援
聴覚障がいのある方に、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行う自治体があります。
医療機関での受診・公的手続き・就職活動・学校行事などで支援が必要な場合、手話通訳者や要約筆記者を無料または低額で派遣してもらえます。
また、障がい者相談支援事業所での生活相談や就労支援事業所でのキャリア相談、なども利用可能です。
暮らしの中での困りごとを整理し、利用可能な制度について詳しく確認しておきましょう。
参考:千葉市『障害者向けサービス』
聴覚障がい6級の方が補聴器購入時に利用できる助成制度
聴覚障がい6級の認定を受けている方は、さまざまな助成制度を活用して経済的負担を軽減できます。
ここでは、聴覚障がい6級の方が補聴器購入の際に利用できる助成制度を解説します。
障がい者総合支援法による補助金制度
補装具費支給制度は、補聴器本体や修理費の実質負担を軽減できる制度です。
国が費用の半分を負担し、都道府県と市町村が各4分の1ずつ負担する仕組みで、原則で利用者負担は1割となります。
補装具費支給制度を利用するには、お住まいの市町村窓口への申請が必要です。
障がい福祉担当窓口で相談のうえ、必要書類を揃えて申請手続きをしましょう。
参考:厚生労働省『補装具費支給制度の概要』
医療費控除の利用
補聴器が必要であると医師に診断された場合、補聴器の購入費用が医療費控除の対象となります。
補聴器購入の際は、補聴器相談医の診断を受け、補聴器適合に関する診療情報提供書を発行してもらいます。
診療情報提供書を持参し補聴器を購入した後は、確定申告で購入時の領収書と診療情報提供書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
自治体独自の制度
多くの自治体では、国の制度に加えて独自の補聴器助成制度を設けています。
自治体独自の制度では、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の方や、特定の年齢層を対象とした助成が多く見られます。
お住まいの自治体で独自の補助が用意されているかどうか、確認すると良いでしょう。
参考:福岡県『福岡県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について』
よくある質問
聴覚障がいにより障がい者手帳の取得を考えている方にとって、具体的な基準や取得方法を知ることは大切です。
ここでは、聴覚障がいに関するよくある質問を解説します。
聴力障がいで5級はもらえる?
聴覚障がいの等級は2級・3級・4級・6級のみで、5級の認定は存在しません。
聴覚の等級は純音聴力検査や語音明瞭度の数値を基準に判定され、等級の中で最も軽い区分は6級となります。
片耳難聴でも障がい者手帳6級は取得できる?
片耳に重度の難聴があり、もう片方の耳も一定の聴力低下がある場合は、6級を取得できる可能性が高いです。
上記で解説したように、6級の認定基準は両耳の聴力が70デシベル以上、片方の耳が90デシベル以上・もう片方の耳が50デシベル以上となっています。
しかし、片耳が完全に聞こえなくても、もう片方の耳の聴力が基準値まで低下していない場合は、6級の認定基準を満たしません。
自分の聞こえの状態を確認するためには、耳鼻咽喉科で詳しい聴力測定を行い、適切な診断を受けましょう。
【まとめ】聴覚障がい6級はどのくらい聞こえるのか
聴覚障がい6級は、両耳の聴力が70デシベル以上という認定基準があります。
70デシベル以上とは、通常の会話音量である60デシベルよりも大きな音でないと聞き取りが困難な状態です。
どのくらい聞こえるかは個人差がありますが、補聴器を使用することで日常生活での聞き取りが改善される場合があります。
また、身体障がい者手帳の取得により、税金の控除や交通機関の運賃割引、補聴器購入時の助成制度など、さまざまな支援を受けられます。
手帳の申請には指定医師による診断書が必要なため、まずは耳鼻咽喉科で詳しい聴力検査を受けてください。
聞こえにくさでお困りの場合は、一人で悩まず専門医に相談し、適切な支援制度を活用していきましょう。
「運営のお悩み」9棟運営の経営者に相談できます
人材が定着しない。収益が伸びない。実地指導が不安。
月額3万円・初期費用0円で、現場を知る経営者が伴走します。