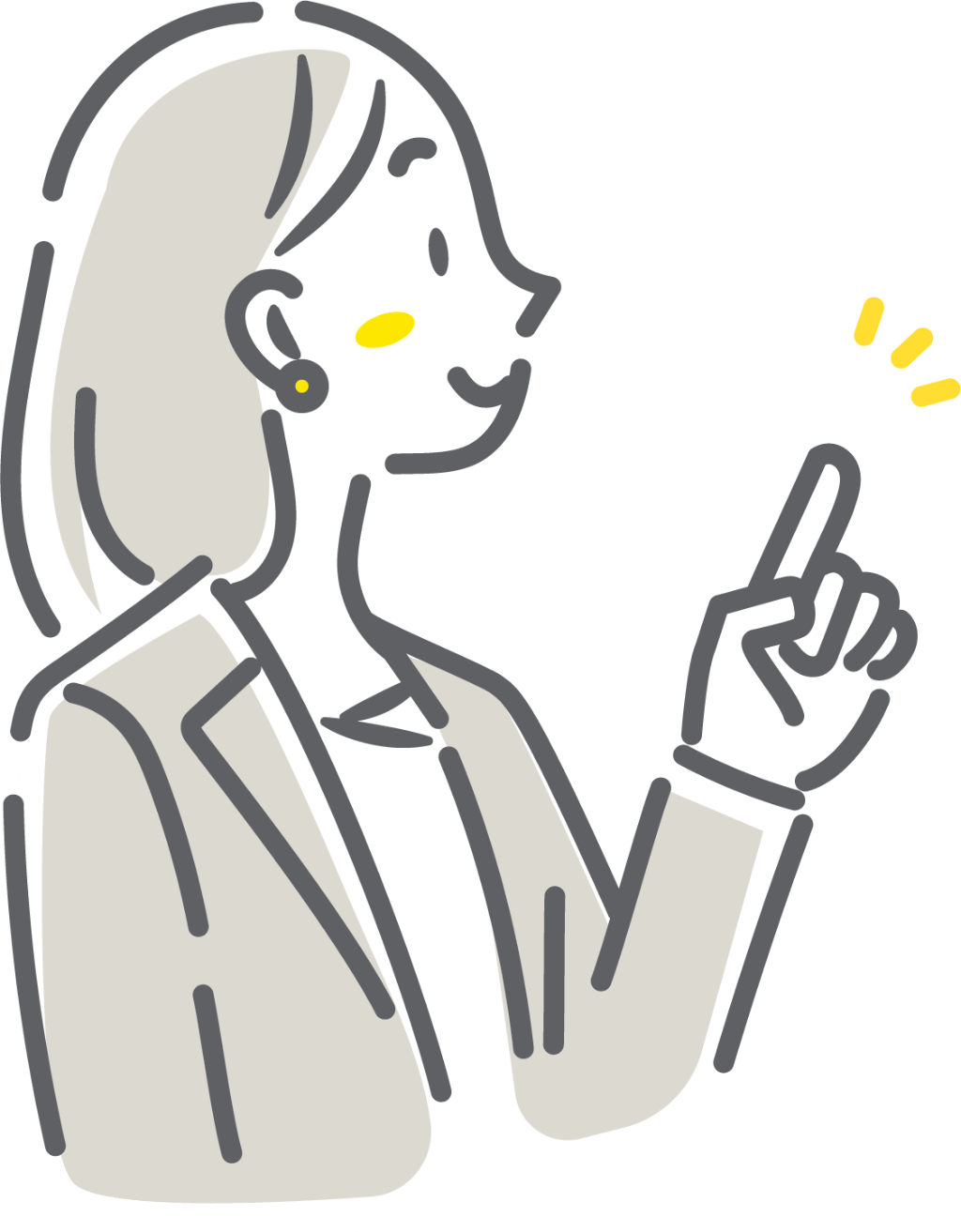療育手帳は、障がいの程度を見直す「再判定」の時期が決められています。
しかし、療育手帳を持っている人全員が再判定の対象なのか、どのように手続きをすればよいかわからない方もいるでしょう。
ここでは、療育手帳の再判定が不要なケースと手続きの方法を解説します。
この記事を読むことで、再判定を受けなかった場合のリスクと更新手続きの必要性がわかるでしょう。
✅️自社9棟運営の現場ノウハウ
✅️チャット・電話で回数無制限
✅️違約金なし・いつでも解約OK
もう、一人で抱え込む必要はありません。
\毎月3社様限定・相談無料/
療育手帳の再判定が不要なケースとは
療育手帳の再判定は、障がいの程度や年齢により不要になる場合があります。
ここでは、どのような場合に再判定が不要になるのかを解説します。
永久判定(終了判定)を受けている場合
療育手帳を保有する方の障がいの状態が安定していると判断された場合、永久判定(終了判定)を受けることがあります。
この判定を受けると、障がいの程度に変化があるかどうかを見直す再判定は不要です。
再判定が不要になると手帳の有効性が維持され、必要な福祉サービスを継続して利用できます。
重度の障がいがある場合
多くの自治体では、重度の知的障がいがあると認められた場合、再判定が免除されることがあります。
これは、障がいの状態が固定していると判断され、改善の見込みが少ないと医学的に認められるからです。
しかし、判定基準は自治体によって異なるため、重度でも再判定が必要な場合もあります。
一定の年齢に達した場合
療育手帳の再判定の時期は各自治体で定められており、年齢によって更新が不要になる場合があります。
厚生労働省の統計を見ると、再判定が必要な年齢の上限は平均35.1歳です。
多くの自治体では、18歳未満の児童に対して数年ごとに再判定期間を設定していますが、年齢が上がるにつれて再判定を不要としています。
参考:厚生労働省『療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究』
自治体の判断による場合
療育手帳制度は全国共通の法律ではなく、各自治体が独自に運用しています。
そのため、再判定の頻度や基準は地域によって大きく異なり、特定の条件を満たしていれば再判定が不要になるケースもあります。
具体的な内容については、お住まいの自治体の担当窓口に確認してください。
療育手帳の再判定を受けないとどうなる?
再判定の期限内に療育手帳の更新を忘れてしまった場合、その後のサービス提供に影響はあるのでしょうか?
ここでは、再判定を受けなかった場合のリスクについて解説します。
障がい者福祉サービスの利用停止
療育手帳の再判定を受けなかった場合、今まで利用していた障がい福祉サービスを受けられなくなる可能性があります。
当然ながら、期限切れの療育手帳は利用できません。
そのため、今まで適用されていた療育手帳による医療費の助成や公共交通機関の運賃割引なども、利用できなくなります。
手当の返納・追徴課税のリスク
療育手帳を保有していると、障がいの程度により障がい児福祉手当や特別障がい者手当などのさまざまな支援が受けられます。
しかし、再判定を受けなかった場合、手当の返納を求められることがあるでしょう。
また、療育手帳の期限が切れていると、所得税や住民税の障がい者控除が適用されなくなり、追徴課税が課される可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、療育手帳の有効期限を確認し、期限内に再判定を受けることが大切です。
再判定手続きを忘れたときの対処方法
再判定の手続き忘れに気づいたら、速やかに自治体の窓口に相談し、状況を説明しましょう。
その際、再判定に必要な書類を確認し、医師の診断書が必要であれば病院の受診予約も行います。
自治体によっては、一時的に手帳の効力を延長する措置を取ってくれる場合もあり、今まで利用していたサービスを継続して利用できる可能性があります。
手続き忘れを防ぐためにも、自治体から再判定通知が送られてきたら早めに更新手続きを進めましょう。
療育手帳の更新手続きの方法
療育手帳の再判定通知を受けたら、期限内に手続きを済ませる必要があります。
ここでは、療育手帳の更新手続きの方法を確認していきましょう。
療育手帳の更新頻度
療育手帳の更新頻度は自治体によって異なりますが、一般的には年齢に応じて更新頻度が決められています。
年齢別の再判定時期を、千葉県船橋市を例に見ていきましょう。
- 18歳未満:おおむね2年ごと
- 40歳未満:おおむね10年ごと
- 40歳以上:再判定なし
このように、年齢によって時期が決められていますが、再判定までに症状に変化があった場合は、自己申告により再判定を受けることもできます。
参考:船橋市『療育手帳に有効期限はありますか』
療育手帳の更新手続きに必要な書類
療育手帳の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 療育手帳
- 再判定申請書
- 本人の顔写真
- 印鑑
必要に応じて、医師の診断書などが求められる場合があるため、更新手続きをする前に確認しておきましょう。
療育手帳の更新手続きの流れ
療育手帳の更新は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。
- 現在保有している療育手帳や申請書など、必要な書類を準備する
- 準備した書類を自治体の窓口に提出する
- 申請書の提出後、面談の日程が決定する
- 指定された日時に、児童相談センターや知的障がい者更生相談所などで面談をする
- 更新手続きが完了した後、新しい療育手帳を受ける
新しい療育手帳の交付までに1〜2カ月ほどかかるため、余裕を持って更新の手続きをしましょう。
参考:独立行政法人福祉医療機構『知的障害者更生相談所』
よくある質問
療育手帳の再判定時期や再判定が不要な方の条件を解説してきましたが、詳しい判定基準などがわからない方もいるでしょう。
ここでは、療育手帳に関するよくある質問について解説します。
療育手帳は18歳を過ぎたらどうなりますか?
療育手帳は、通常18歳までに知的障がいが認められる方に交付されますが、その状態が継続している場合、18歳以上になってからも手帳の取得が可能です。
年齢によって障がいの程度を判定する機関が異なり、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で知能検査を実施します。
療育手帳のAとBの違いは何ですか?
厚生労働省は、療育手帳の障がいの程度と判定基準を「重度(A)」と「それ以外(B)」に区分しています。
- 重度(A):知能指数がおおむね35以下で食事・着脱衣・排便・洗面等日常生活の介助を必要とする、または異食・興奮などの問題行動を有する
- それ以外(B):重度(A)のもの以外
自治体によっては、この区分をさらに細分化している場合や、B判定より軽度のC判定を設定している場合もあります。
具体的な条件は、お住まいの担当窓口に確認してください。
参考:厚生労働省『療育手帳制度の概要』
【まとめ】療育手帳の再判定が不要になるケースがある
療育手帳の再判定とは、障がいの程度を見直すために実施される制度です。
しかし、永久判定を受けている方や重度の知的障がいがある方、自治体が定めた年齢に達した方は、再判定が不要になる場合があります。
再判定が必要な方は、必要書類を準備し、更新の手続きを進めましょう。
療育手帳の期限が切れてしまうと、今まで受けていた福祉サービスなどの継続ができなくなってしまいます。
万が一、手帳の更新を忘れてしまった場合は、速やかに自治体に連絡をすることが大切です。
✅️自社9棟運営の現場ノウハウ
✅️チャット・電話で回数無制限
✅️違約金なし・いつでも解約OK
もう、一人で抱え込む必要はありません。
\毎月3社様限定・相談無料/